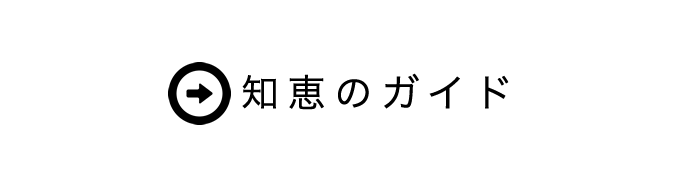江戸時代はどんな生活をしていた?庶民の暮らしぶりについて
2017.9.13

江戸時代の庶民の生活はどんな生活をしていたのか、気になりませんか?
時代劇のような長屋暮らしは本当だったのか?実は江戸時代の庶民の生活ぶりを記録した資料がほとんど残っていないとは!?
江戸時代の庶民の生活についてまとめてみました。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
ヨーロッパ旅行では○○に注意が必要!楽しい海外旅行にするには
憧れのヨーロッパ旅行!美しい街並みや世界遺産などが多く、景色を堪能するのもSNS映えする写真をたくさ...
-

-
子猫がミルクを吐くときの原因は!?怖い病気が潜んでいる場合も
子猫がミルクを吐くのは、飲ませ方や量が関係している場合もあります。 しかし頻繁な嘔吐や下痢は病...
スポンサーリンク
記事の概要・目次
江戸時代の生活は服装やおしゃれの仕方で庶民など身分が分かる!?
江戸時代の人は身分や年齢によって服装や髪形に決まりがあったため、その人の身なりをみればどんな家なのかが分かりました。
江戸の町人は裕福ではありませんので、江戸の町人の男性の着物は新品ではなく、古着屋で購入するのが一般的で質素な服装をしていました。
おしゃれは羽織でしていました。羽織を羽織るのが粋とされていて、江戸時代の長い歴史の中でもそれぞれの時代に流行のデザインがあったそうです。
江戸の町人の奥さんは、着物の上に今でいうエプロンを着用するのが一般的でした。
髪型も決まっていて丸髷という髪型が主流です。
エプロンは前掛けや前垂れと言って、家事などで着物が汚れるのを防ぐ目的があります。
女性も着物は限られた数しか持っていなく、男性同様に新しく買う場合も新品ではなく古着を買うのが一般的です。それでも、数少ない着物を大切に着るためにエプロンをして着物が汚れないようにしたのでしょう。
江戸時代の庶民が暮らした家や生活とは?
江戸時代には士農工商の制度が確立していました。江戸の町人は、士農工商の工商に当たります。
表通りに面したところに2階建ての商家、その裏に平屋の長屋があり、町人は長屋に住んでいました。
現代のように、長屋の土地や建物の所有者とそこを管理する大家がいたそうです。
「大家を親と思え、店子を子と思え」という言葉を知っていますか?店子とは家を借りている人、借家人のことです。
このような言葉があるように、大家が長屋の家賃を徴収したり法的な権利のない店子の身元保証人となって世話をし、長屋住民達の絆は固かったそうです。
なお、町民が一日に稼ぐのは平均で350~410文程度だったそうです。
ちなみに現代の価値では1文がいくらなのかはっきり言うことが出来ないそうですが、当時は団子が1串5文という説があります。
江戸の町民は宵越しの金を持たないと言われることがありますが、収入の低さが理由だったと思います。
また、江戸時代には火事が多く財産があっても燃えてしまいます。誰も火事の保証はしてくれませんので、金目の物は持たないようにしていたとも考えられます。
銭湯の文化が普及したのも、火事の原因にならないように家にお風呂を作らなかったためだと言われています。江戸の銭湯は庶民のコミュニケーションの場になっていたのでしょう。
江戸時代の庶民の生活を記した資料は消されてしまった!?
実は、江戸時代の生活ぶりを記した資料が今はほとんど残っていないということを知っていますか?
長く栄えたのに江戸時代の生活ぶりや建物がほとんど残っていないのにはこんな理由があるとささやかれています。
江戸時代が終わりを迎え、明治時代が始まりました。今の時代の政治を見てても分かるように、前の物を否定する傾向にありますよね。
新政権は自分たちの正当性を主張するために、旧勢力を無くそうと江戸時代の建物や資料を破壊消滅させていった・・・かもしれません。
こういう事は珍しい事ではなく、歴史をみると世界各地で起こっていることで、国や部族の争いで勝った方は負けた方を支配するために徹底的に反勢力分子を叩き潰した場合もあります。
なお、江戸文化が西洋文化に比べて劣っているとして、江戸時代の名残を潰していった側面もあるでしょう。
現存している資料は少ないですが、本当はもっと多くの資料や建物などがあったと思います。
江戸時代の庶民の生活ぶりは質素でも外国人には幸せそうに見えた!?
江戸時代は身分の差で生活ぶりが大きく違うのは有名で、偉い人はいい暮らしをしていても庶民は長屋で貧乏暮らしのイメージです。
スイッチ一つで電気がついて蛇口を捻れば水が出てる何不自由のない現代の日本人からすると、江戸時代の長屋暮らしは狭い部屋に家族で住み、水道も電気もなくトイレなど衛生面もプライバシーもないのは幸せとは言い難そうな生活に思えるでしょう。
江戸よりも文化が発展している西洋人も、現代の日本人と同じイメージを抱いて日本を訪れたことでしょう。しかし、幕末にやってきた外国人は日本人が幸せそうに見えていたそうです。
英国使節団員「印象的だったのは男も女も子供も皆幸せで満足そうに見える事だった」「個人が共同体のために犠牲になる日本で、それぞれが幸福で満足そうに見えるのが驚くべき事実」
ロシア艦隊勤務の英国人「健康と満足は男女と子供の顔に書いてある」
江戸よりも文明が進んだ西洋人からみると、生活ぶりは質素で遅れているように見えたと思いますが、それでも日本人が幸せそうに見えたそうです。
また、個人主義の西洋人からすると公に尽くす行為は犠牲で不幸な事に見えても、日本人は幸せそうに見えたと言葉を残しています。
江戸時代の農民の生活とは?
江戸時代の農民は武士に支配され、衣食住すべてにお金をかけることが出来ず貧乏な身なりや生活ぶりだったイメージがありますよね。
農民の一日は、夜明け前に起きて日が昇ると畑で農作業をし、日が沈む頃に帰宅して、夕食後も藁を編んだり農具の手入れをしていた・・・訳ではなかったそうです。
慶安の御触書に農民は「早起きし、朝は草を刈り、昼は田畑を耕作し、夜は縄を綯い、俵を編むなどそれぞれの仕事をきちんと行う事」とされているのです。
もしも、農民が先に書いたようにきっちりと働く人ばかりなら、こんなことは書く必要はありません。つまり、意外と朝寝坊したり真面目に働かない農民も多かったのでしょう。
なお、農民も公に休日が定められていたそうです。
休めるのはお盆やお正月とお祭りなどで、年間30~50日はお休みがあったそうです。植物を相手にする農業に休日はないイメージなので、公に休みがあるのは意外ですよね。
しかし、好きなように休みを決めたり、○日に1回休みなどの決まりではなく、田植えや稲刈りの時期などは休みなく働いていたようです。
しかも、決められた休みではない日に休むと処罰されていたというから驚きです。
- 雑学・知識