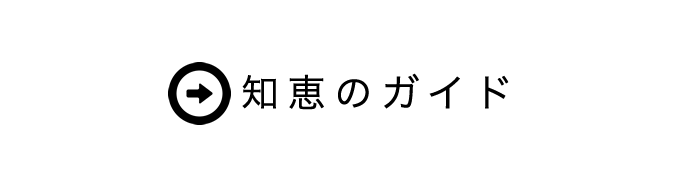脳の記憶力に限界を感じる…記憶力のメカニズムと脳トレ方法とは
2017.9.21

脳の記憶力には限界があるように感じたことはありませんか?
いくら勉強を頑張っても、テストで結果を出せない…。
少し前に顔を合わせた人の名前が思い出せない…。
そのような経験をされたことは一度はありますよね。
人間の記憶力を伸ばす方法がないか、調査してみました!
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
小学生ならみんなしてる!?習い事をしてないのは間違いではない
今はほとんどの小学生が何かしら習い事をしているようです。 でも、中には家庭などの方針によっては...
-

-
子供のわがままは自我の芽生え!4歳児のわがままと向き合う方法
子供も4歳になると自我も芽生え、体格も良くなり、わがままがパワーアップします…。 魔の2歳児を...
-

-
子供に勉強を教える親が絶対にしてはいけないことは「怒ること」
子供に勉強を教えるのって大変ですよね? 勉強がわからなくて頭を抱えている子どもを目の前に「どう...
スポンサーリンク
記事の概要・目次
脳の記憶には限界があるもの?
脳の記憶は無限なものではないため、限界はあります。心理学的に表現すると、覚えている部分は『顕在意識』、記憶が薄れ忘れてしまったほとんどは『潜在意識』として膨大なデータが眠っていると言えます。
“忘れる”という現象は、その記憶が引き出される頻度が低下した時に起こります。大脳は常に新しいことを“記憶”しようと、空きスペースを確保しようと働きかけます。
顕在意識を自由にコントロールできる容量には限りがあるため、引き出される頻度が低い記憶は潜在意識に移されてしまいます。これは効率が良いアウトプット行うためでもあるのです。
パソコンのハードディスクも容量が大きいものだと、膨大の情報の中から欲しい情報を引き出すのに時間がかかりますよね。しかし、少ない容量と情報量の中から引き出すことは簡単です。脳も同じ原理だと言えるでしょう。
脳の記憶が限界になる容量ってどのくらいなの?
人の記憶力には個人差がありますが、脳がもっている記憶の容量は膨大なものなのです。
ハンガリー出身の数学者で、現在のコンピューター動作原理を考案したジョン・フォン・ノイマン氏は、「人間の記憶量は、10の20乗ビットと同程度」と試算しています。『ビット』とはコンピューターで使われるデータの最小単位で、「8ビット=1バイト」となります。
「アルファベット1文字=1バイト」程度のデータ量と言われているため、イノマン氏が試算した人間の記憶量をパソコンで表すと「100GBのパソコン、約1億台分」に相当するそうです。人の脳の記憶量は、このように膨大なものを持っています。
「人はモノを忘れてしまう機能がある」ため、実際にはもっと記憶量は少ないのではないかという意見もあります。しかしそれを差し引きしても、記憶の容量は大きいのです。あとは、どのようにして上手に活用するかで、記憶力を最大限に発揮させることができます。
脳の機能を最大限に活用!記憶を限界まで持たせるには復習を
記憶した情報をできるだけ長く保つには、記憶してから1カ月以内の『復習』が大切になります。1カ月を超えると、短期的に記憶保存する『海馬』から記憶が消えてしまいます。
そのため、1カ月過ぎてからの復習は『復習』ではなく『初めて記憶したこと』となってしまいます。そのため、復習のタイミングとしては1カ月以内に行うのが好ましく、長期記憶に変えて定着させることができます。
では、1カ月以内の復習にはどのタイミングで、どの程度するのが望ましいのでしょうか。勉強したことを記憶として定着されるには“復習を反復して行う”「反復学習法」をすることです。一番やりやすい反復学習法のリズムは「1週間」ですね。今日勉強したことを、来週の同じ曜日に行う。再来週、再々来週と4週にわたって同じ曜日に同じ勉強をすることで、記憶を定着させることができるでしょう。
そのため、学生の方は曜日ごとに勉強する科目を決めるというのも、一つの手段になります。平日に5科目を勉強して、休日は作文の練習や資料集めなどの時間に充てることができます。
資格の勉強などをする方は、自分でいくつかの分野に区切って学習することをおすすめします。効率よく反復学習をすることで、確実に記憶を定着させましょう。
記憶に頼りすぎない!脳の記憶があいまいでミスすることも
ある人材情報サイトでは、男性214名に対して「職場の上司に怒られると焦った失敗談」についてアンケート調査を行いました。そこで一番多かったのが、「頼まれていた仕事を、うっかり忘れていた」ということです。
その他に「電話応対で、取り次ぎメモを残し忘れた」、「会議中に居眠りをして、持っていた資料などを落とした」、「上司宛ての電話で、相手の名前を聞き忘れた(聞き間違えた)」、「資料や企画書に誤った記載があった」という体験談などがあります。
調査の結果から見ると、「忘れる」ことに関するミスが多いということが分かりました。仕事をしているとやらなければならないことが多く、大量の情報もひっきりなしに飛び交います。その中で「うっかり忘れた」というミスは、誰もが経験することでしょう。
そのようなミスが起きる原因は、記憶力が低く注意力が散漫だからというわけではありません。脳のメカニズムからすると、このようなミスは起こしやすいのです。それを回避しようと記憶力や注意力などを鍛えようとしても、ほとんど効果はありません。
記憶に頼りすぎないよう、まずは「メモを取る」ことを習慣づけることが大切です。頼まれた仕事、電話応対の時は必ずメモを残しましょう。目に留まるところに貼っておくことで、「忘れた」というミスを防ぐことができます。
ランニングは健康維持だけじゃない!?脳の記憶力を鍛える脳トレにも
身体のトレーニングや健康維持を目的として、ジョギングやランニングをする人が多いでしょう。しかし、これらの運動は脳にも良い効果が与えているのです。
運動機能と脳の機能は、切り離すことができない密接な関係を持っています。そのため、体力づくりだけの目的にとどまることが無く、脳を活性化させることもできるのです。脳トレを考えている方は、運動も実践してみるといいでしょう。
特にランニングなどの有酸素運動は、脳に良い効果をもたらすとされています。それは、「海馬への適度な刺激」があるためです。海馬は記憶を司る部分なのですが、本来は年齢を重ねるについれて海馬が委縮してしまいます。
しかし、運動を行うことで、海馬に刺激を与えて活性化されます。記憶力を伸ばしたい若者はもちろんのこと、記憶力の衰えが気になり始めた中高年や高齢者にもおすすめの脳トレ方法となります。
- 学習・教育