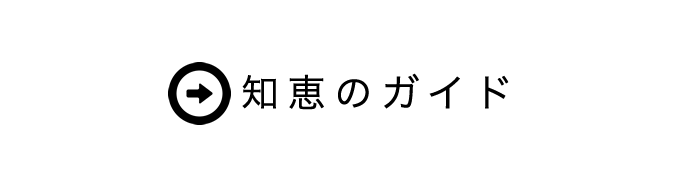子供が言葉につまる!その原因と対処法・考えられる病気について
2017.11.14
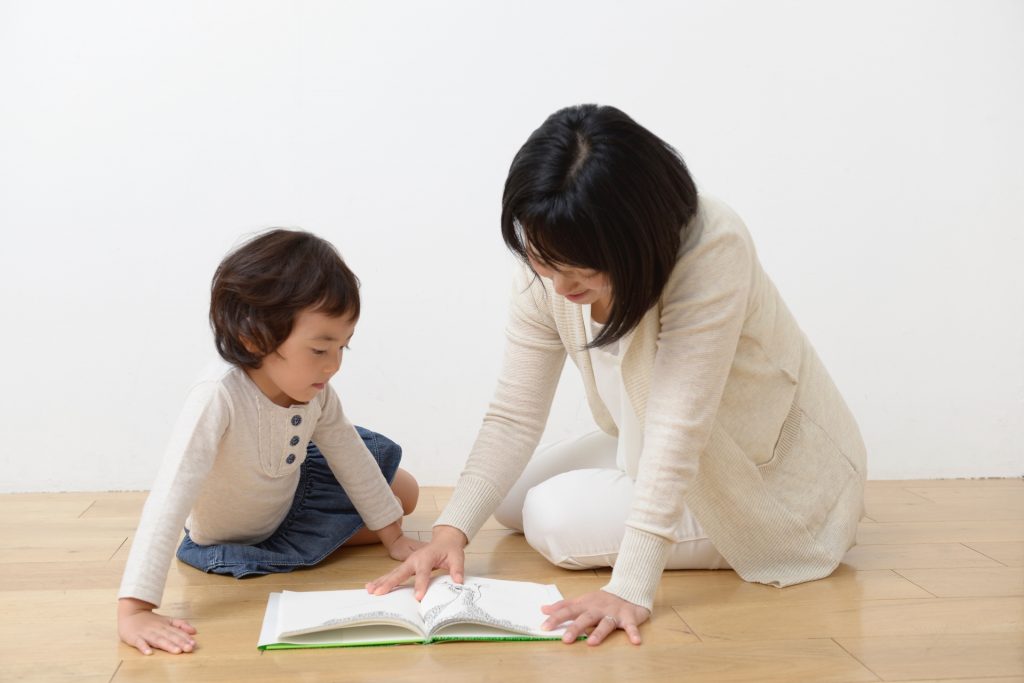
子供が言葉を話している時、言葉がつまるような様子があれば心配になりますよね。
子供が言葉につまってしまうことを「吃音症」と言います。
そこで今回は、この症状が起きやすい原因や対処法についてお伝えします。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
別居をすることになって子供が転校しなければならない時の対処法
両親の離婚を前提として別居をすることになった時、子供に直接関係してくる問題は「転校」の事です。 ...
-

-
子供に勉強を教える親が絶対にしてはいけないことは「怒ること」
子供に勉強を教えるのって大変ですよね? 勉強がわからなくて頭を抱えている子どもを目の前に「どう...
スポンサーリンク
記事の概要・目次
子供の言葉がつまる症状について
子供が成長するにあたって、幼児期から幼少期にかけては急激に言葉の発達が進みます。
親が子供の吃音に気が付くのもこの頃が多いですいが、まだ上手に言葉を反すことが出来ない子供が大人のように話をしようとすることで、言葉がつまってしまうことはよくあることです。
このため、吃音でつまっていつのか、ただ単にどもっているのかを判断するのは難しいことになります。
また、こういったことは自然に解消していくことがほとんどになります。
子供の吃音は、女の子よりも男の子に多く見られ、3倍ほど多いと言われています。
子供の吃音で特徴的なものが、男女差があるということになります。
原因は色々ありますが、男の子の方が女の子よりも脳の神経の発達が遅く、腹式呼吸になるまでの期間が長いということが考えられます。
性別の違いだけで吃音が見られるのであれば、大きくなっていくとともに症状が改善されていくと考えられますが、精神的なものが原因の場合の吃音もありますので、原因を特定するのは容易な事ではありません。
子供が言葉につまる吃音症とは
言葉がつまってしまうことを「吃音症」と言います。
■吃音症(きつおんしょう)
会話の途中で言葉がつまってしまい、声をだせなくなってしまうという特徴があります。
言葉を連続でスムーズに話すことが出来なくなり、第一声がなかなかでないという病気になります。
「どもり恐怖症」とも言われていて、WHO(世界保健機関)では、吃音症のことを「会話の流暢性とリズムの障害」としています。
吃音症を障害認定している国もあり、日本でも医療機関を受診すると健康保険が適用されて受診することが出来ます。
吃音症が発祥する年齢は、言葉を話し始めるころが最も多くなり、5歳以下の幼児で約5%、学校に通い始める頃の子供で約1.2%、成人では0.8~1.2%ほどになります。
発症する年齢は子供の割合が高いですが、幼児期に吃音症を自覚することはあまりありません。
また、どんな時にどもるのか、どもりやすい場面はどんな時なのかには個人差があり、大人になってからも吃音症に気が付かないことが多いです。
この症状を自覚すると治りにくくなるとも言われています。
吃音症の場合は、緊張を感じるからどもるのではなく、どもることを気にするから緊張すると考えられていて、意識してしまうことで症状が悪化してしまうこともあります。
子供に吃音症の症状が見られた場合は、病院で相談してみると良いでしょう。
また、どもってしまうことをあまり意識しないで生活するようにしてみましょう。
子供が言葉につまる時に親がしてはいけないこと
幼稚園に通い始めたり、新しい環境で生活するようになった時など、環境の変化が起きたときに言葉につまってしまうことが多いです。また、興奮状態ににあるときやストレスを感じている、疲れているなどの時にも言葉につまることがあります。
こういった症状も半年ほどして環境に適応できるようになってきたら徐々に見られなくなってきますが、自分の言葉がスムーズに出ないことに気が付くと、話すことを恥ずかしいと感じるようになり、言葉を話すことに恐怖感を覚える子供も出てきます。
親は子供のサポートを行ってあげましょう。
子供が言葉につまってしまう時は、以下のことに注意しましょう。
■言葉につまった時に口をはさんだり、言葉を直すことはしない
■言葉をゆっくり言わせたり繰り返し言うことはしない
■言葉を反復させない
■言葉に詰まってしまっても、反し終えるまでプレッシャーを与えない
■子供と会話をする機会を増やし、話をするときも大きな声で話す
■症状が悪化しないようにストレスのかからない生活を心がける
子供が言葉につまってしまうことは、自然改善していくケースも多くあります。
言葉につまってしまったり、どもってしまうことは早めに治療を行うことでより効果を得ることが出来ます。
また、深刻な症状が見られる場合は専門医を受診して診察してもらいましょう。
子供の言葉のつまりに気が付いたとき~先輩ママの体験談~
子供の言葉がつまってしまうことに気が付いた先輩ママさんの体験談をご紹介します。
「我が家の長女は3歳半頃から言葉につまるようになってきました。その頃は次女を妊娠中で、ちょうど私のつわりがひどかった頃です。
また、それまで通っていた保育園と違う保育園に通い始めたりと、環境の変化も起きていました。
長女は妹の誕生を心待ちにしていて、産まれてからもとってもかわいがっていましたし、新しい保育園での生活もとても楽しんでいました。
でも、この頃も言葉にはつまっていましたね。
保育園の先生に聞いてみると、言葉がスムーズに出ない時は一度落ち着かせてから「せーの」と声掛けを行って話をさせると良いと言われました。
我が家では言葉がつまってしまうことをそれほど深刻にはとらえていなかったため、「話したいことがいっぱいあるんだね、ゆっくりお話しして教えてね」というように声掛けを行いながらのんびり構えていました。
長女が言葉につまらなくなったのは5歳ころです。
今となっては、親も本人もあまり気にしていなかったので『そんなこともあったな』という感じで思い出しています。」
吃音が見られた時にしてあげたいことは?
子供に吃音が見られた時にしてあげると良い事があります。
子供の言葉がつまっていても、最後まで話を聞いてあげることが大切です。子供が話した内容に共感し、一生懸命に話が出来たことを評価してあげましょう。
言葉につまることは悪いことではありません。このことを欠点と捉えてしまうかもしれませんが、どんな人にだって欠点はあります。完璧な人間なんていないのだということを子供に教えてあげて、気持ちを大きく持つことが大切だと教えてあげましょう。
言葉がつまってしまうことに対して感じているストレスを取り除き、気持ちを楽にさせてあげることで、スムーズに言葉が出てくるようになります。
また、吃音が見られるからと言ってそのことを隠したりすることもよくありません。
言葉が聞き取りにくくて相手に嫌な思いをさせてしまうのではないかと思うかもしれませんが、はじめに「言葉がつまることがあって聞きにくいことがあるかもしれません」と伝えておくようにしましょう。
そうすると、話を聞く相手も話を親権に聞いてくれるようになりますし、思い切っていってしまった方が舞う割の人からも理解されるようになって、人間関係もスムーズに進むようになります。
- 学習・教育