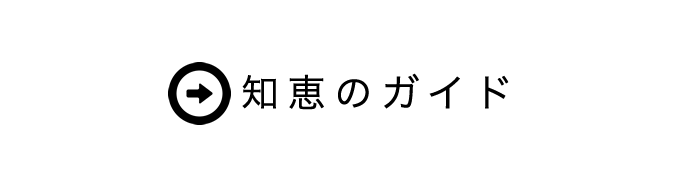子供を抱っこしていいのはいつまで?愛情を伝えるのは大切
2017.9.11

子供ってすぐ抱っこして欲しがりますが、それはいつまで続くのかと不安なお母さんもいるのではないでしょうか?
また、これはいつまで続けてもいいものだろうかと心配なときもありますよね。
そこで、いつかは卒業が来る子供の抱っこについて考えてみました。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
うちの子供は勉強ができない!お母さんのお悩みにお答えします!
「うちの子供はどうして勉強が出来ないのかしら・・・」そんな悩みを抱えている親御さんもたくさんいますよ...
スポンサーリンク
記事の概要・目次
いつまで続く?抱っこでしか寝ない子供
うちの子は抱っこでしか寝ないんです・・・なんて嘆いているお母さんもいるかと思います。
毎日抱っこで自分の睡眠もままならないお母さんにとって、この状態はいつまで続くのだろうかと不安になりますよね。
でも、安心してください!抱っこにはいつか卒業が来るのです。
例えば、卒乳をする頃になると、子供も自分でも移動ができるようになり運動量も増えます。そうすると、自然と自分で眠れるようになってくるのです。
ですから、いつか来るその日まで、少しでもお母さんも眠れる時は眠るようにして、赤ちゃんと付き合っていきましょう。
抱っこができる今この時期を大切にして、愛情をいっぱい伝えてあげてくださいね。
時には、お父さんに寝かしつけをお願いするのも良いでしょう。抱っこ紐を活用するのも良いですね。
子供を寝かしつけるのに、抱っこ紐はいつまで使っていいの?
子供を寝かしつけるために、抱っこ紐を使っているお母さんも多いでしょう。
しかし、抱っこ紐を使っての寝かしつけは、だんだん子供が大きくなっても使っていると、お母さんへの負担が大きくなってしまいます。
負担が大きくなると、肩こりや腰痛などがひどくなり、日常の生活にも無理が出てきてしまいます。
子供にとって、お母さんが動けなくなってしまうことの方が大変ですよね。苦しんでいるお母さんの様子を見て、子供も悲しくなってしまうかもしれません。
ですから、ある程度子供が大きくなってからの寝かしつけには、抱っこ紐は使わずに、別の寝かしつけの方法を取る方が良いでしょう。
そばに一緒に横になっているだけで、自然と寝てくれるようになっていきますよ。
子守唄を歌ったり、背中をさすったり、トントンしてあげるのも良いですね。
子供の「抱っこして」は、いつまで続くの?
赤ちゃんの頃は、抱っこは日常的で寝かしつけも抱っこのまま寝かせることが多かったりしますよね。
2歳くらいになってくると、外ではスタスタと一人で歩いていても、お家の中などでは「抱っこして~」とすぐに甘えてきたりします。
例えば、ご飯を作る時でも抱っこしながら作ることもあったり、少しでも降ろそうとすると、慌てて自分の足や腕を巻き付けてきたり。
このように、お家の中などの「抱っこして~」4~5歳くらいになっても続くこともあるようです。
このくらになってくると幼稚園などに行くようになってるので、外では自我が芽生え、お友達に見られたら恥ずかしいと思い「抱っこして」とはあまり言わなくなります。
ただ、お家の中ではまだまだお母さんに甘えたい時期なんですよね。
いずれは抱っこできなくなると思って、抱っこできるうちにお母さんはたくさんお子さんを抱っこしてあげてくださいね。
親にたくさん抱っこされた子供は安定して育つ!?
子供をいつまでも抱っこするのは、子供にとって良くないのではないかと心配になっているお母さんはいませんか?
しかし、抱っこをたくさんしたからって子供が弱い人間になるわけではありません。逆に、そのような子供は自立が早くなるのです。
人は自分が愛されていると実感できると、安心ができるのです。子供も親の愛情を感じることで、とてもしっかり育つのです。
そして、抱っこをたくさんされて育った子供は頭も良くなるとも言われています。
これは愛情を感じて育つことで、情緒も安定し、勉強にも意欲的になるからだそうです。
また、親の愛情で心が満たされている子供は、外の世界においても自分を持って強く生き抜くことができるのです。
子供の人格の形成にとってもスキンシップはとても大切なのです。
たくさん子供を抱っこし、愛情を伝えることで、心の不安を取り除いてあげてください。
きっと手のかからない真っすぐな子供へと成長するでしょう。
大きくなった子供の「抱っこして」には理由がある
幼児の場合の「抱っこして」は、目的地に着くまで抱っこして欲しかったり、自分が眠たいから抱っこして欲しいなどの理由が多いです。なので、長い時間抱っこをしなくてはならなかったりもします。
しかし、大きくなった子供の「抱っこして」には、また違う理由があるのです。
それは、自分の不安を受け止めて欲しいことだったりします。
例えば、幼稚園で先生に怒られた、仲の良い友達とケンカしてしまった、などお母さんの知らない間に起きた出来事について不安な気持ちを抱いたりしているのです。
そして、お母さんに伝えたいけど、伝えられない、表現できなくて、その不安な気持ちから「抱っこして」となってしまっているのでしょう。
ですから、そんな時は抱っこしてあげることで、子供の心の不安を取り除いてあげましょう。
きっとすぐに子供の気持ちも落ち着くでしょう。
- 学習・教育