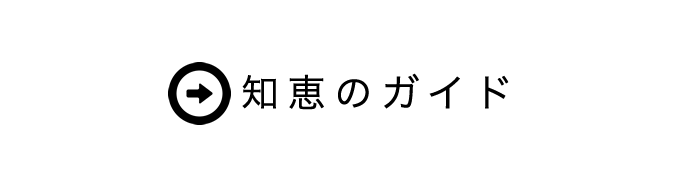ピアノコンクールに参加するだけでレベルアップに繋がる理由
2017.8.31

ピアノを習っていると勧められるのが、コンクールへの参加です。ただコンクール自体に賛成派、反対派がいるほど意見が分かれるものでもあります。
しかし、ピアノコンクールに参加こと自体に意味があり、参加することでレベルアップにも繋がるとの意見もあります。それはなぜなのでしょうか。
一番大切なのは、出場する子供の気持ちです。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
別居をすることになって子供が転校しなければならない時の対処法
両親の離婚を前提として別居をすることになった時、子供に直接関係してくる問題は「転校」の事です。 ...
-

-
うちの子供は勉強ができない!お母さんのお悩みにお答えします!
「うちの子供はどうして勉強が出来ないのかしら・・・」そんな悩みを抱えている親御さんもたくさんいますよ...
-

-
子供を寝かしつける方法は?1歳の子供がぐっすり寝てくれる方法
子供を寝かしつける時、なかなか寝てくれないと大変ですよね! 1歳くらいの子供を寝かしつける時、...
スポンサーリンク
記事の概要・目次
ピアノコンクールに参加するだけでレベルアップに繋がるの?
ピアノコンクールは参加すること自体に意味があります。
ピアノコンクールに向けて毎日努力しますし、晴れの舞台で大勢の方を前に演奏する喜びも感じることができます。ピアノコンクールへの参加を目標にすることで、努力と技術が得られるのです。
ピアノコンクールはゴールではありません。目標を示すものであり、成長できる道しるべでもあります。
子供のころから一つのことをずっとやり続けている方はどのくらいいるでしょうか。
おそらくほとんどいないのではないでしょうか?
それはピアノにも言えることで、多くの人は歳を重ねるごとにピアノから離れてしまうものです。それは続ける機会がなくなってしまうから。
目標があって成果がでれば続ける楽しさもありますし、たとえ音楽家にならなくても、ピアノを学んで上達する喜びを知ることで生活も輝きます。
ピアノコンクールは、学校で定期的に行われる「試験」のようなものです。
自分のレベルを確認し、わからない場所を認識する機会でもあります。
コンクールで競い合うことも大切ですが、お互いを讃え合う気持ちも必要ですし、その中から得られることも大きいでしょう。
ピアノコンクールはレベルごとに分けられているの?
ピアノコンクールはレベルごとに分かれている場合があります。
あるコンコールを例にご紹介します。ある楽器店主催のコンクールは、3つの部門に分かれています。
■コンクール部門
小学生から中学生までが対象で、A~Dまでのレベルに分かれています。予選と本選があります。
課題曲はなく、自由曲での演奏になります。
ピアニスト2名から個別に評価してもらえ、本選以上は地区予選、エリアファイナル、グランドファイナルと進んでいきます。
地区予選からは課題曲と自由曲の審査になります。
出場料は予選が8.500円、本選が10,000円。
■チャレンジ部門
幼児から小学2年生までが対象で、審査はありません。自由曲を演奏し、こちらもピアニスト2名から個別に評価を頂けます。
出場は1回のみで、出場料は6,500円。
■一般部門
高校生以上が対象で、審査はありません。自由曲を演奏し、ピアニスト2名からの個別講評が頂けます。出場料は12,000円。
となっています。
コンクールによってそれぞれ内容もレベルも違いますのでご注意を。
ピアノコンクールはレベルに合ったところから始めてみよう!
レベルをアップさせたいがために、子供に難易度の高い曲を弾かせるのはあまりよくありません。
子供が無茶をすれば弾けるかもしれませんが、肉体的にも音楽的にも早すぎる曲を弾くことで、強引なピアノの弾き方や単なる演奏コピーロボットになりかねません。
練習をしていると、「もっと力を入れて大きい音で!しっかりクレッシェンドして!」とつい指導してしまいます。
ですが、弾くのはまだ体格的にも精神的にも未熟な子供です。
自分の中でしっかり曲を理解して弾いているのであれば問題ないですが、もし言われるまま、ただ大きい音を出しているだけだとしたらどうでしょうか。
それは本当に音楽を感じてピアノを弾いているとは言えませんよね。
ピアノ教育は何でも早熟に進めてしまう傾向もあります。
まずは、大規模のコンクールではなく、子供のレベルに合ったコンクールから始める方が良いのかもしれません。
子供のピアノコンクール出場に賛成派、反対派それぞれの意見とは
■コンクールには向き不向きがあるのではと思います。
小さい子ほど言えるのですが、コンクールは負担やプレッシャーが大きいものです。そのため、本来音楽を楽しむべきものが嫌いになってしまう場合もあるからです。
■コンクールに出場するためには日々の練習が欠かせませんし、何よりお金も掛かります。
その子の素質や性格はもちろん、家庭環境も見極めた上で、コンクールに出るか出ないかを見極める必要があるのでは。
■音楽は本来楽しむものです。点数で評価されるものでもありませんし、競争する必要もないのでは?
特に子供の場合は、コンクールにそれほどこだわる必要もないですし、良い刺激を受けたり、緊張感を味わったり、努力の結果が報われるなど、教育的な面に目を向けることも大切だと思います。
■目標をもって練習するのは良いことですが、競争や結果だけに捕らわれるのはよくない。
■同年齢の子供たちのレベルも見れますし、今後どのような勉強をしていけばいいのかを、親子共々具体的なイメージを持つ機会になる
■発表会は、たとえ仕上がらなくてもカットや簡単なアレンジで対応できます。
でもコンクールは子供自身も難しいことにチャレンジすることもできますし、指導者や保護者も一緒に音楽を追及していけます。結果的にピアノの上達に繋がるので、コンクールには賛成です。
必要なのはピアノコンクールを楽しめるくらいの前向きな気持ち
コンクールへの参加によって自信を失ってしまわないか不安になる方はたくさんいるでしょう。
コンクールに参加する方は年々増えていますし、参加した多くの方は、親子共々成長できる、今後の課題や欠点を知ることもできる言います。さらなるレベルアップが見込めるというのです。
だからと言って、全ての人がコンクールに向いている訳ではありませんし、何よりも本人の意思が大事です。
コンクールへの考え方は人それぞれなので、先生や親や本人の気持ちを考慮して考えることが大切ですし、ピアノが好きで音楽が好きだという気持ちがないと上達もしません。
コンクールは人前で演奏し、評価され、出場者同士で競い合ってしまうものです。それに対して前向きな気持ちを持っていることも重要です。コンクールを楽しめるくらいなら安心でしょう。
毎日ひたすら練習し、審査で高い評価をされた人は次の段階へ進み、最後は何人かに絞られて受賞者が決まるのがコンクールです。
多くの参加者は通過できずに終わってしまいます。思ったより低い評価を受けて自信を失ってしまうこともあるでしょう。
ただ、今までの努力や練習に費やしてきた時間を無駄に感じるのはあまりにも悲しすぎます。
結果はどうであれ、ピアノへの情熱が失われないようにしたいですね。
- 学習・教育
- PREV
- 旦那が料理に文句をつける!いい加減にして欲しい!
- NEXT
- 寝起きの辛い吐き気!妊娠初期の対策方法!