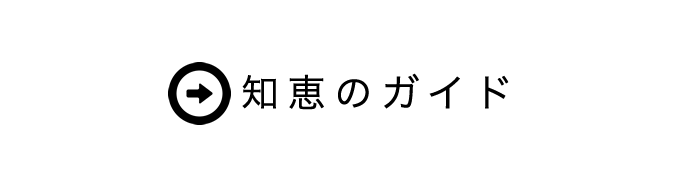中学生の勉強に親は介入すべき?親としての関わり方を教えます
2017.9.12
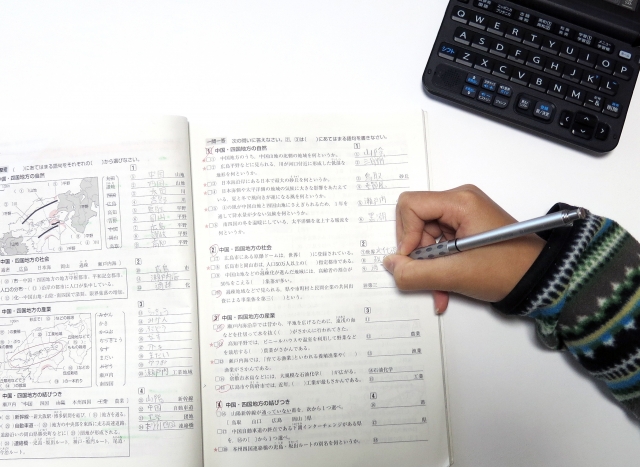
小学校とは違い、より専門的になる中学校の勉強。そこでつまづいてしまう中学生が多いといいます。
そんな中学生の勉強に親はどう関わっていくべきなのでしょうか?小学生の時のように親が教えるべき?それとも塾に任せた方がいい?
親と中学生の勉強との関わり方について説明します。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
子供のわがままは自我の芽生え!4歳児のわがままと向き合う方法
子供も4歳になると自我も芽生え、体格も良くなり、わがままがパワーアップします…。 魔の2歳児を...
スポンサーリンク
記事の概要・目次
中学生の勉強に親は介入すべき?
小学生の時ならまだしも、中学生ともなれば自分から勉強するもの・・・と思っていても、実際にはできていない子供もいます。
そのため、親が「ちゃんと勉強しなさい。」と言うこともあるでしょう。
しかし、勉強自体が嫌いな子供、授業に大きく遅れている子供に対しては「勉強しなさい。」と言っても勉強しなかったり、勉強の方法が間違っている場合があります。
勉強は、習慣づけて行うことが大切です。その習慣がつくまでは、親が介入しなくてはいけないでしょう。
「介入」というのは、勉強を教えるということではありません。昔と違って、学習内容は変わっています。そのため、親が教えることはやめましょう。
親としてやってあげることは、わからないことを調べる時に、どうしたらいいのかを教えてあげることです。答えを教えることではありません。「ここにやり方が載っているよ。」などと何を見たらいいのか、ということを言ってあげるのです。
授業についていけない子供の場合は、何がわからないかが自分でわかっていない場合が多いです。今やっている教材を見直してみましょう。
教材が難しすぎるということはないですか?その子の実力にあった教材を用意してあげましょう。そして自分で答えを出せるように、何を調べたらいいのかを親として教えてあげましょう。
中学生の勉強に親として付き添うのも必要!
中学生の子供の勉強に、親はどう関わっていくべきか・・・そう悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
ある人は中学1年の2学期までは、付き添って勉強を教えていた、と言います。そして少しずつ一人でやらせるようにし、受験生となる中学3年の時には独り立ちしたそうです。
その子の場合、中学1年の3学期頃から好きな科目は一人でやらせるようにしたそうですが、苦手な科目については親が見ていたと言います。
しかし反抗期ということもあり、そのうち親が手伝うのを嫌がるようになっていったとか・・・でも苦手な英語は遅れてしまうと取返しがつかなくなるので、中学2年の3学期までずっとついていてあげたそうです。
そのうち高校生になると自分から塾に行きたいと言い、高校3年になると成績はグンと上がって行ったそうです。そのため、センター試験でも良い成績を取れたようです。
その人が言うには、親が介入してその後手を離したら、後戻りはしないこと、手を離していくのは、得意な科目にすること、この2点だと言います。
塾に行きなくない中学生の勉強に親はどう関わっていくべき?
中学生になると、塾へ通い始める子供が増えてきますが、塾へ行きたくない子供を勉強させるために親はどう関わっていけばいいのでしょうか?
【中学1年】
中学校になると、先生の科目別になり、より専門的な授業になります。定期テストのための対策もしなくてはいけません。
中学1年の家庭学習は、まず中学校の勉強に慣れるための勉強をしていくことが大切です。まずは宿題をしっかりとすること、そして宿題がない日には問題集をさせるようにしましょう。毎日続けて勉強する習慣をつけさせてあげるのです。
【中学2年】
2年生にもなると、中学校の勉強にも慣れてきたことでしょう。部活に入っている場合は先輩として忙しくなってきます。そのため、家庭学習の時間が少なくなってくるかもしれません。そうなると、効率的に勉強する必要があります。
2年生の後半になると、意識しなくても受験という2文字が頭の中に浮かぶようになります。目指す高校によっては、そろそろ塾通いを考えなくてはいけないでしょう。
【中学3年】
中学校の最後の1年になります。受験に向けて、苦手な科目についても考えなくてはいけません。
夏休み前までには、苦手な科目・苦手な分野がどこなのか振り返り、夏休み中に勉強するようにアドバイスしてあげましょう。
塾に行っていれば、中学生の勉強は親が教える必要はない?
塾に行っていれば、親は何もしなくてもいい・・・そう考えていませんか?
もちろん、勉強は塾の先生が教えてくれます、親が教える必要はありませんし、内容が難しいので教えることがムリな場合もあるでしょう。
しかし、親がやってあげなくてはいけないことがあるのです。まずは「聞くこと」です。
勉強のやり方は昔と今では違っています。教科書の内容だって変わっています。子供が勉強のことを聞いてきても、公式や解き方を教える必要はありません。
もし子供に質問されたら「お母さんの時はこうやっていたよ。」と経験談で話してあげればいいのです。それなのに「お母さんはわからないから、先生に聞いてみたら?」などと言ってしまうと、お母さんは自分の勉強に興味がないんだな~なんて子供は感じてしまいます。せっかくやる気を出そうとしているのに、やる気も出なくなってしまいます。
親として、勉強のためになることを言ってあげましょう。
中学生の定期テストの効率的な勉強方法は?
中学生になると定期テストに直面しますが、その勉強方法がわからない子供も多いようです。
そんな子供には、親の力が必要になってくるでしょう。
テストが近くなってくると、先生も重要な部分がしっかりと教えてくれているはずです。授業中にしっかりとノートをとっているようであれば、ノートを何度も見るように言ってあげましょう。理解していないところがあるようであれば、そこを何度も読み返すようにアドバイスするのです。
暗記が必要な科目は、単語カードを活用しましょう。数学は、とにかく問題をたくさん解くようにしましょう。計算に慣れることによって、ミスも少なくなります。
一人で勉強するよりも、リビングで勉強する方が集中できると言います。子供のタイプによっても違うかもしれませんが、リビングの方が安心できるという子もいます。
勉強しない子供に一度勧めてみるのも良いかもしれません。
- 学習・教育